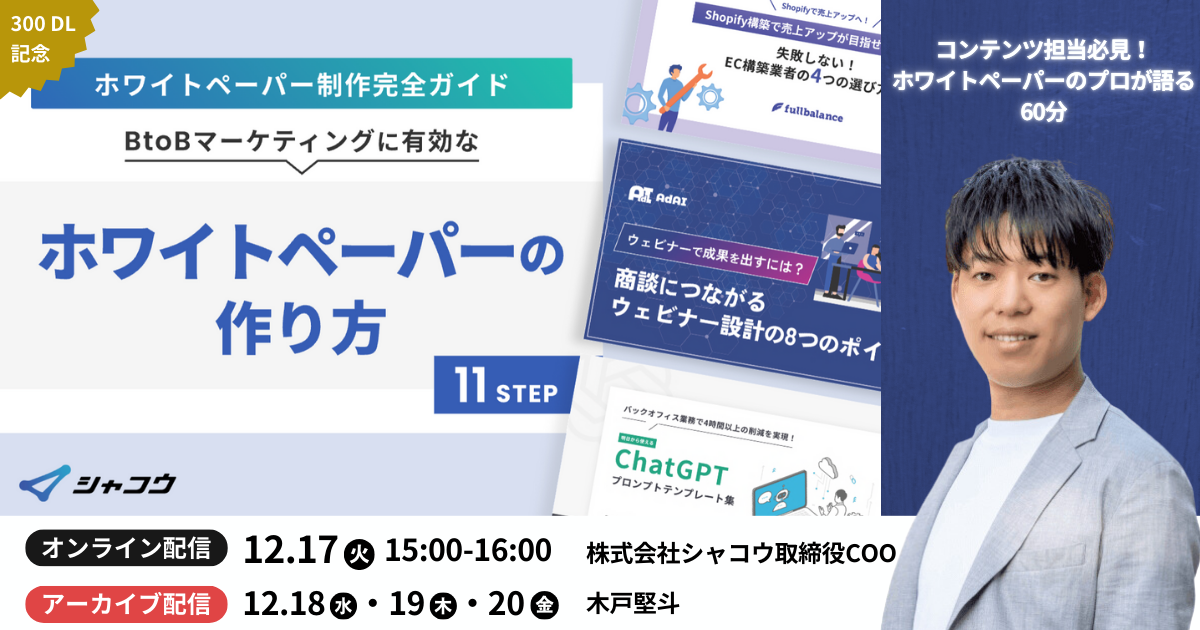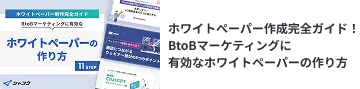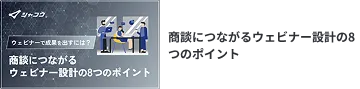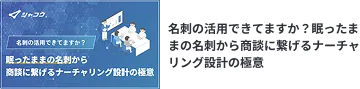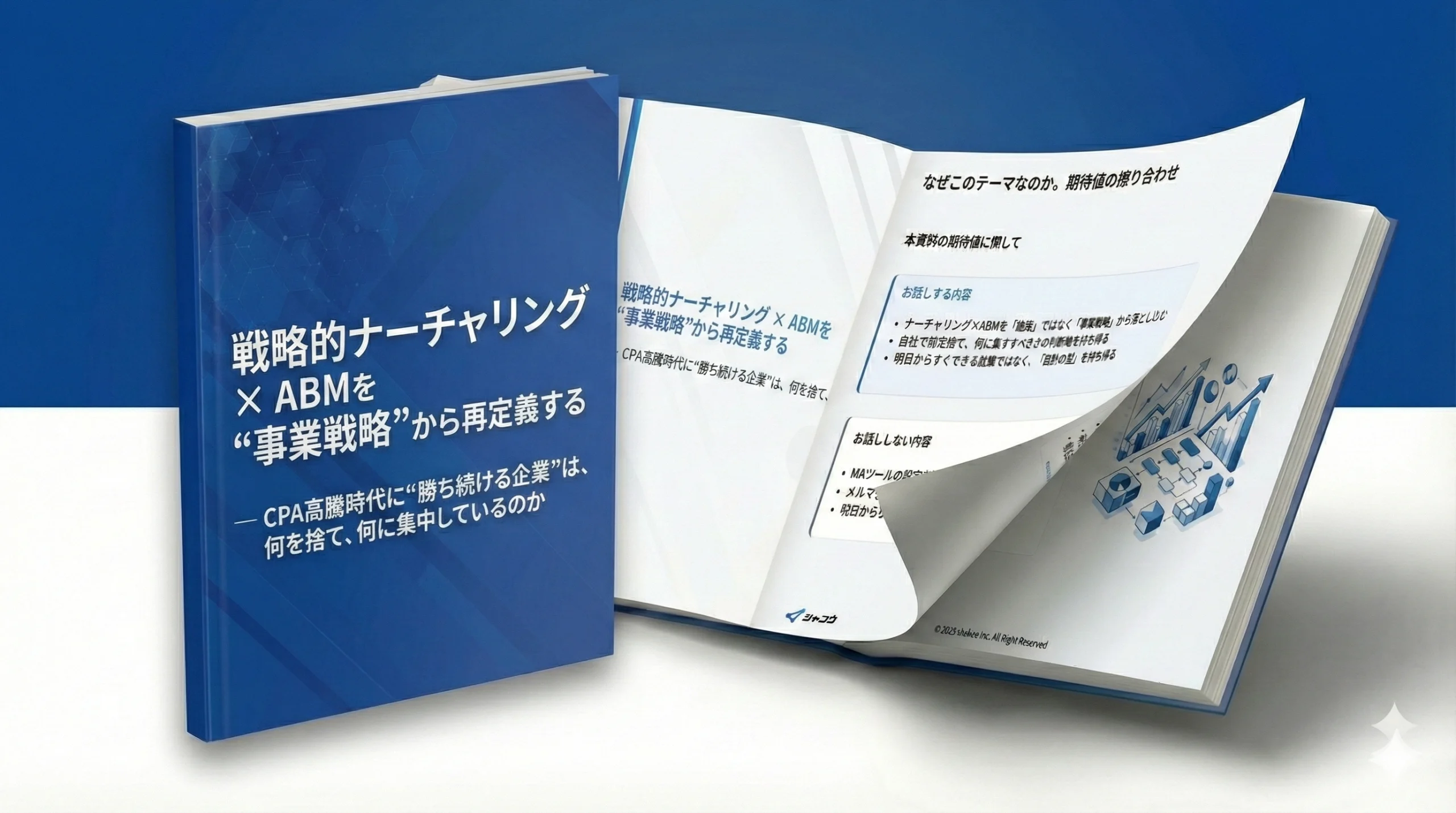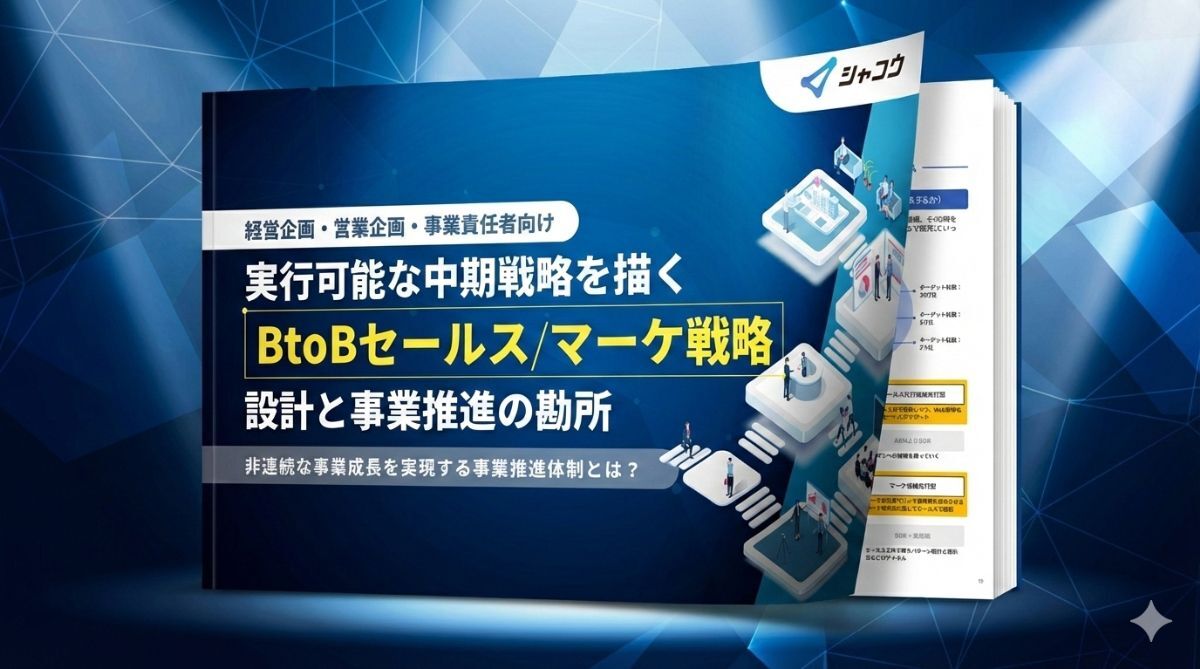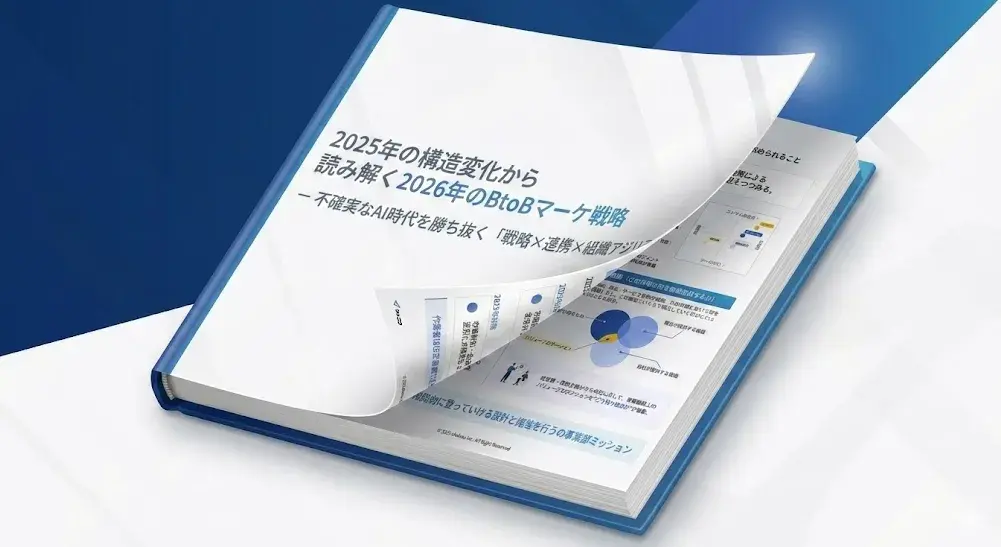BtoBマーケティングの現場で「ホワイトペーパーを活用したいが、何から手をつけるべきかわからない」と悩む方は少なくありません。
本記事では、シャコウが開催したウェビナー「ホワイトペーパー制作完全ガイド11STEP」の内容をもとに、ホワイトペーパーの基礎から制作フロー、成果につなげる活用術までをわかりやすく解説します。
本記事は株式会社シャコウが運営するYouTubeチャンネル「BtoBマーケ研究所」のウェビナー動画、「ホワイトペーパー制作完全ガイド11STEPをプロが解説する60分|企画・設計・デザイン・マーケ戦術まで解説【ウェビナーアーカイブ】」のレポート記事です。資料はこちらからダウンロードください。
ホワイトペーパーとは?サービス資料との違いやそのメリット
まずは、ホワイトペーパーの基本的な定義を整理しながら、サービス資料との違いや具体的なメリットについてわかりやすく解説します。
サービス資料との違い
そもそもホワイトペーパーとは、顧客の課題解決を目的とした情報提供の資料です。サービス資料や営業資料とは異なり、ユーザーにとっての価値を提供することに重きが置かれています。
主なメリットとしては、リード獲得、リード育成、顧客満足度の向上などが挙げられます。

失敗しないホワイトペーパー設計のコツ
「入門ガイド」や「イベントレポート」などは作りやすい反面、サービスへの関心が薄い層が集まる傾向があります。一方、「課題解決型」「導入事例紹介」などは見込み度が高く、受注にもつながりやすいのが特徴です。
重要なのは2軸の設計です。
- 縦軸:資産性(長期活用できるか)
- 横軸:サービスへの関心度

ホワイトペーパーは資産性が高い
ホワイトペーパーの活用チャネルは多岐にわたり、オウンドメディア・広告・メルマガ・テレアポ・ウェビナーなど、あらゆるマーケ施策と組み合わせやすい資産型コンテンツです。

ホワイトペーパーマーケティングを成功に導く!部署内での共通意識
ホワイトペーパーマーケティングで失敗したというお話をよくお聞きます。シャコウで、ホワイトペーパーマーケティングを行う上でどのような社内認識があるのかをお話しします。
ホワイトペーパーの役割
ホワイトペーパーの役割は、受注につながるリードをインサイドセールス(IS)にバトンパスしていくことです。リードの質と量のバランスを意識する必要があります。特に「受注につながるかどうか」はシャコウでは非常に意識している部分です。

重要なのは情報収取フェーズでの早期接点づくり
昨今、情報収集フェーズが非常に重要になってきています。インターネットの発達によって、営業担当との初商談まで、つまり情報収集の段階で、意思決定の57%が完了しているというデータあります。
そのため、情報収集フェーズから、早期に顧客接点を持ち、信頼関係を構築することが重要です。

フェーズごとに刺さるコンテンツづくりが重要
シャコウでは全てのフェーズにおいてコンテンツを制作し、全てのフェーズにおいて情報発信し、第一想起を獲得できるようにしています。

ホワイトペーパーの制作体制
ホワイトペーパーを制作する際に必要な人員や、内製と外注の違いを解説しました。
ホワイトペーパーを作る際のチームメンバー
ホワイトペーパーを制作する際、基本的には以下の役割が必須です。
- ディレクター
- ライター
- デザイナー
加えて、品質管理を行う
- 編集者
をチームに含めるケースもあります。

ホワイトペーパーを作る手段【内製?外注?】
内製の場合は制作費を削減できるのがいちばんのメリットです。また、社内でノウハウを蓄積できる点、その後の展開ができる点も特徴です。
一方、外注の場合は短期間で高クオリティの資料ができる点が大きなメリットです。ただ、その分費用がかかるため、予算を考慮する必要があります。
特に内製で制作する場合、進行管理や品質担保の難しさがあります。初めての場合は、要所だけ外注を活用するハイブリッド型もおすすめです。

ホワイトペーパーの作り方
ここからは、実際の制作プロセスを11のステップに分けて解説します。

STEP1|作成の目的の明確化
最初に必ず行うべきは「このホワイトペーパーは何のために作るのか?」の目的整理です。リード獲得なのか、ナーチャリングなのか、商談化支援なのか──目的によってターゲットも内容も構成も変わります。
また、読者が今どのフェーズにいるのか(課題を感じ始めたばかり/比較検討中/決裁直前)によって最適なテーマも異なります。目的と想定読者の状態を合わせて設定しましょう。

STEP2|自社の立ち位置・強みの明確化
制作の起点となるのが「自社のバリュープロポジション」の言語化です。
ホワイトペーパーは最終的に自社のサービスや強みを知ってもらい、「信頼→興味→相談」へつなげるものです。SWOT分析や3C分析を活用しながら、他社と比較したときの差別化ポイントを言語化しておきましょう。

STEP3|ターゲットの設定
業種・企業規模・職種・役職など、ターゲット像を明確に定義します。あわせて、ターゲットが抱えるであろう「課題」や「関心事」「情報収集のチャネル」などもセットで整理すると、後の企画設計がスムーズになります。

STEP4|企画・テーマの決定
ターゲットを設定できたら、ターゲットが抱える悩みや関心が見えてきます。ホワイトペーパーは、抽出した悩みや課題を解決できる内容を含めたテーマに設定しましょう。
既存顧客へのアンケートやインタビュー、営業・カスタマーサクセスからのフィードバックなどを活用し、「読者が本当に困っていることは何か?」を定性的・定量的に把握しましょう。

STEP5|ストーリー・ゴールの決定
「読者に読んでもらったあと、どういうアクションを期待するか?」を決めておくのも重要です。例えば、トライアル申込やサービスページへの遷移、個別相談などが挙げられます。
ゴールが決定したら、構成(ストーリー)を組み立てます。特にBtoBでは、「課題に共感→解決策提示→自社の強み」という流れが自然です。ここで注意すべきは「自社のアピールが唐突に入らないこと」です。自然な流れで「この会社なら頼れそう」と思ってもらえる設計が鍵です。

STEP6|トンマナの決定
読者の業界や慣習に応じて、適切なトンマナ(トーン&マナー)を設計します。たとえば、レガシー業界向けなら「読みやすさ・親しみやすさ」を重視、IT・スタートアップ業界向けなら「スタイリッシュさ・先進感」が求められるなど、ターゲットごとに最適な見せ方は異なります。

STEP7|リサーチの実施
差別化されたホワイトペーパーを作るには「情報の深さと一次性」が不可欠です。
- 業界調査・トレンドリサーチ
- 競合他社の資料分析
上記のようなリサーチを通して、ネット検索では得られない視点や気づきを盛り込めると、読者の信頼を得やすくなります。また、自社での独自データや事例を含めることで、より差別化が可能になります。

STEP8|構成の作成
企画・ストーリーに基づいて、目次(構成)を設計します。構成では、各章が「読者の課題に対する解決の道筋」をたどるよう設計することが重要です。
タイトルの付け方も重要で、「誰向け」「何がわかる」が一目で伝わる表現にしましょう。また、自社の宣伝やサービス紹介のページが多すぎると、ユーザーの課題を解決しきれないことがあるため、特に注意しましょう。

STEP9|ページ配置の決定(ラフの作成)
ここでは「どの内容を、どの順番・レイアウトで配置するか」を決定します。文章だけでなく、図や表、アイキャッチ、キャプションなど視覚情報の構成も含めてラフを作成するのがおすすめです。
この段階で「全体のボリューム感」「見せ方の方向性」を明確にしておくと、次工程のデザインがスムーズに進みます。

STEP10|ライティング・デザイン作成
構成・ラフに沿って、本文の執筆とデザイン作業に入ります。
- ライティング:キャッチコピー/見出し構成/図解説明文/読みやすさ
- デザイン:視認性/統一感/トンマナの反映
文章は「結論ファースト」で構成し、余計な前置きを減らすことで、読了率が上がります。

STEP11|編集・最終チェック
最後は、全体を通しての見直しフェーズです。以下のポイントをチェックしましょう。
- 誤字脱字・表記ゆれはないか
- トンマナが崩れていないか
- 読みやすさ・構成の論理性は担保されているか
- CTA(コンバージョン導線)が明確か
- 情報量が目的に対して適切か(厚すぎる/薄すぎる) など
「読者の行動を後押しする」視点での最終確認を行い、ホワイトペーパーとしての完成度を高めていきましょう。

チャネルごとのホワイトペーパー活用術
ホワイトペーパーは「作って終わり」ではなく、どのように活用するかで成果が決まるコンテンツです。ウェビナーでは、制作後の活用法についても詳細に語られており、以下のチャネルごとのポイントを紹介しました。

Webサイト・LPでの活用
サイトに訪問したユーザーの中には、「まだ問い合わせまではしたくないが、情報収集はしたい」と考えている層も多くいます。そうした層に向けた「ハードルの低いCVポイント」としてホワイトペーパーは非常に有効です。
特にBtoBでは、問い合わせ前に多くの情報収集が行われるため、サイト回遊ユーザーの取りこぼしを防ぐ役割としても重要です。

広告連携での活用
広告とホワイトペーパーの組み合わせは、CPA(顧客獲得単価)を下げつつ、質の高いリードを獲得する手法としても注目されています。

テレアポでの活用
直接的な営業接点においても、ホワイトペーパーは効果を発揮します。特にテレアポでは、「まずは資料だけお送りします」とハードルを下げるトークの武器になります。
同様に、フォーム営業でもハードルを下げたCV地点としてホワイトペーパーが有効です。

オウンドメディアとの連携
SEO記事のCVを最大化するためにも、ホワイトペーパーは強力な武器になります。SEO記事のCVをサービスLPとするのはハードルが高いため、ハードルを下げたホワイトペーパーをCV地点とするのが有効です。
記事読了後の「もう少し深く知りたい」というタイミングで資料を提示することで、離脱を防ぎながらリード情報を獲得できます。

メルマガとの連携
ホワイトペーパーとメルマガの相性は非常に高く、「売り込み感のない有益な情報提供」が可能になるのが大きなポイントです。
開封率やクリック率を高めたいときにも、課題解決型のホワイトペーパーは重宝されます。さらに、ホワイトペーパーを起点に顧客の関心領域や検討段階を可視化できるため、インサイドセールスとの連携もしやすくなります。

まとめ
ホワイトペーパーは、見込み顧客との信頼関係を築くためのコンテンツ資産です。その真価を発揮するには、緻密な顧客理解にもとづいた上流設計と、質の高いアウトプットを確実に実行するチーム体制が欠かせません。
ホワイトペーパーマーケティングの鍵は、上流設計の思考力と、下流での実行力の両立です。「知っている」「聞いたことがある」という知識レベルから一歩進んで、「設計できる」「動かせる」状態へ。その一歩を踏み出すことで、コンテンツはリードを呼び込み、ナーチャリングを支え、営業の武器となります。
▼本レポートの内容をより詳しく知りたい方は、ウェビナーのアーカイブをぜひご覧ください。
本記事は株式会社シャコウが運営するYouTubeチャンネル「BtoBマーケ研究所」のウェビナー動画、「ホワイトペーパー制作完全ガイド11STEPをプロが解説する60分|企画・設計・デザイン・マーケ戦術まで解説【ウェビナーアーカイブ】」のレポート記事です。資料はこちらからダウンロードできます。


 お問い合わせ
お問い合わせ